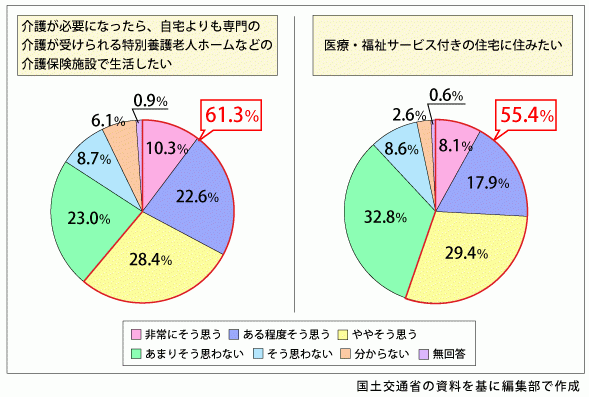国土交通省は6月30日、「住生活に関する国民アンケート」の調査結果を発表した。それによると、介護が必要となった場合、自宅より特別養護老人ホームなど介護保険施設での介護を望む人が6割超に上った=グラフ=。
調査は今年1-2月、国土交通行政インターネットモニター1199人を対象に実施。994人(82.9%)から回答を得た。回答者の年齢は60歳代以上が全体の17%、50歳代以下が83%だった。
調査結果によると、老後の理想の住まい方について「介護が必要になったら、自宅よりも専門の介護が受けられる特別養護老人ホームなどの介護保険施設で生活したい」との項目に対し、「非常にそう思う」「ある程度そう思う」「ややそう思う」と肯定的に答えた割合は61.3%に上った。一方で、「あまりそう思わない」「そう思わない」を合わせた否定的な回答は31.7%にとどまった。
また、「医療・福祉サービス付きの住宅に住みたい」との項目でも肯定的な回答が55.4%に上り、医療や介護といったサービスの付いた住まいへの居住意向が多いことが分かった。
さらに、「一人暮らしをする場合、24時間生活を見守るシステムがあるとよい」が76.8%を占めた。また、73.9%の人が「自然に恵まれた田舎よりも、娯楽施設や公共施設、医療・福祉施設などへのアクセスの良い市街地に住みたい」と回答した。
2010年07月01日 16:23 キャリアブレイン