口が渇く病気ードライマウスが、若い人から高齢の方まで広い年齢層に広がっています。少し口が渇く程度から、渇きすぎて話ができない、味がわからない、舌がひび割れてしまったなど、非常に多くの病状があります。ドライマウスで悩んでいる方は推定で八百万人といわれていますが、圧倒的に女性に多く、四十~六十歳代が中心です。
ドライマウスの治療は、原因ごとに対処します。歯科医は、問診や口腔(こうくう)内診査を行い、適切な処置をします。しかし、薬剤による副作用が原因と診断した場合、その薬剤の使用を中止できれば良いのですが、それによってリスクが生じることがあります。薬剤の変更、減量、中止に関しては、必ず、疾患の主治医の先生と相談の上で行い、口腔の乾燥症状のケアや、乾燥に伴う口のトラブルなどの治療を行います。
また、歯周病になると唾液の分泌量が減り、口が渇くという現象が目立ちます。そして、口が渇くと、口の中が洗い流されないため不潔になりやすくなります。かかりつけの歯科医院で定期的な歯のクリーニングや歯周病の治療が必要です。
福島民報 2010.11.1
記事一覧
ドライマウスと歯周病 女性に多く40~60代中心
歯科最前線 岡山大学病院 歯周病治療 全身疾患予防へ外科処置も
歯周病の大きな問題は、全身に悪影響を及ぼす点。「放置すれば誤嚥性肺炎、糖尿病、心筋梗塞や早産、低体重児出産などを招く可能性が高まる」治療は感染源の除去、炎症の制御、歯周組織の形態改善が柱。まず歯磨き法を改善しながら、スケーラーという器具を使い、歯垢が石灰化した歯石を取り除く。
歯肉溝が深くなった歯周ポケットがあると、痛みがないよう局所麻酔をして歯石を除去し、抗菌剤などを注入する。予防法は磨き残しをなくすことだが「最近と免疫のバランスが崩れると発症し、未成年でも重症化する。自覚症状がなくても年1回、誕生月には歯科を受診して検査を」と語る。
山陽新聞 2010.11.1
知っておきたい 隣接医学あれこれ
元気な高齢者像が見えなければならない。全国の市町村の保健師に、「あなたの住んでいる所で80~85歳の元気な高齢者を一人だけ選んで、次のことを尋ねてみてください」とお願いした。
調査対象の全国3千人を超す高齢者の平均年齢は83歳で、男女比は4対6であった。調査結果からは、元気(健康)な高齢者に共通の興味深い37の特徴がみえてきた。中でも8割以上の人が当てはまる項目が12項目あり、その12項目を「活動的余命を延ばす12カ条」として利用することとした。
その内容は①食事は1日3回規則正しく②よく噛んで食べる③野菜、果物など食物繊維をよく摂る④お茶をよく飲む⑤タバコを吸わない⑥かかりつけ医を持っている⑦自立心が強い⑧気分転換のための活動をしている⑨新聞をよく飲む⑩テレビをよく観る⑪外出することが多い⑫起床、就寝時間が規則的、である。
日歯広報 2010.11.25
認知症ケア専門士、患者家族の8割超が知らず
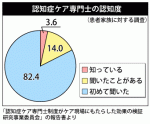
認知症ケアの専門的な知識と技能を備えた「認知症ケア専門士」について、患者を抱える家族の8割余りは、その存在自体を知らないことが、日本認知症ケア学会の調査で分かった。一方、家族の8割近くは認知症に対する専門的なケアが必要と感じていることも明らかになった。
長引く中耳炎の背後にGERD
難治性の中耳炎で名大病院耳鼻咽喉科准教授の曾根三千彦氏の元に最近訪れた
75歳の女性。鼓膜切開を施行しても改善しなかったその患者に奏効したのは、消
化性潰瘍やGERDの治療に用いる酸分泌抑制薬「PPI」だったそうです。
曾根氏は地域の診療所に協力を依頼し、成人患者253人(平均年齢63.4歳)に
問診票を用いてGERD合併率を調査。その結果、誘因不明の滲出性中耳炎患者では
、約47%がGERD症状を有していました。一方、中耳炎以外の症状で受診した患者
のうち、GERD症状があったのは約13%で、中耳炎患者の方が合併率が有意に高い
ことが分かったそうです。
中耳への胃酸逆流のメカニズムは解明されていませんが、「耳管周囲の浮腫と
耳管機能障害により、咽頭と中耳腔内の圧格差が生じ、間欠性に逆流内容物が中
耳腔に達している可能性が考えられる」と曾根氏は話しています。
ホント?「キシリトール入りのお菓子なら虫歯にならない」
キシリトール入りのガムやアメ、タブレットなどが巷にあふれている昨今。「キシリトール入りのお菓子なら虫歯にならない」と思う人もけっこういるけど、本当はどうなの?渋谷区幡ヶ谷の坪田歯科医院・坪田泰幸院長は言う。「キシリトールは虫歯の発生を抑制する(抗ウ蝕誘発性)といった表現がされることがありますが、これは消費者の誤解を招きやすい表現です。少なくとも、キシリトールに”虫歯を治す”働きはないんですよ」
ガムを噛むことは、唾液の分泌を促し、虫歯予防が期待できる。さらに、キシリトールを含めた糖アルコール系甘味料は、再石灰化に必要なカリシウムの供給源になる性質もあるという。ただし、「キシリトール入りのお菓子なら大丈夫」というわけではない。「キシリトール入り」であって、甘味料の100%がキシリトールではなく、虫歯をつくる他の糖が入っている可能性もあるので、ご注意を。
夕刊フジ 2010.11.6
声かけはコミュニケーションの第一歩
「いやだ! 助けて!」
Nさんが口腔ケアをしようとすると、いつも暴れ出すキミ(仮名)さん。半年
前、Nさんが初めて担当した利用者さんで、重度の認知症の方です。キミさんは、
口腔ケアをしようとするといつも、叩いたり蹴ったりしてNさんを拒絶していま
した。
どうしたらいいか分からず、Nさんは毎回オロオロするばかり。訪問するたび
に「わたしは嫌われてるから、キミさんは一生口を開けてくれない」と落ち込み、
泣きながら帰ることもあったそうです。
そんなある日、Nさんにアドバイスをくれたのはグループホームの施設長でし
た。
「前の歯科衛生士さんは、もっと落ち着いたトーンでキミさんに話しかけていた
わよ。お話ししながらマッサージなんかして『キミさん、今日お口のケアする?』
って聞いてからケアを始めていたわね」
Nさんは自身の行動を思い出してハッとしました。キミさんに聞こえるように
と大きな声で話しかけていたり、認知症の方との接し方が分からず、訪問すると
すぐ口腔ケアを始めようとしていたのです。
反省したNさんは、声かけから見直すことにしました。先輩や、訪問先の看護
師さんの声かけを参考にし、声の大きさ、高さ、話すスピード、タイミングなど
に気をつけていきました。
すると、3ヶ月ほどが過ぎた頃から、キミさんは暴れて口腔ケアを拒否するこ
とがなくなっていったのです。相変わらず口は悪いけれど、最近では自分からイ
スに座り口を開けてくれるように。
「声かけって、訪問を始める前はそんなに意識してなかったんですけど、コミュ
ニケーションをとる上で本当に大切だな、って実感しています」とNさんは言い
ます。
やさしく静かな声で語りかけるNさんに、文句を言いつつも口を開けてくれる
キミさん。半年前の二人を想像できない、穏やかな光景でした。
第7回症例検討会
12月11日道北口腔保健センターにて摂食・嚥下リハビリテーション症例検討会が開催されました。当日は、小樽歯科医師会の館先生、キユーピー(ユは小さい文字ではないそうです。)からの基調講演ならびに、旭川日赤、札幌歯科医師会、当センターからの症例と4時間近くにわたり発表されました。参加者は、歯科関係のみならず医療機関、施設、ケアマネさん、栄養士さんなど多職種にわたり50名ほどでした。当院からもお声を掛け施設職員さん、栄養士さん、ケアマネさんの参加ありがとうございました。今後も開催するときは宜しくお願いします。
過去ログ
- 2025年12月 (15件)
- 2025年11月 (24件)
- 2025年10月 (26件)
- 2025年09月 (20件)
- 2025年08月 (22件)
- 2025年07月 (21件)
- 2025年06月 (12件)
- 2025年05月 (13件)
- 2025年04月 (5件)
- 2025年03月 (11件)
- 2025年02月 (11件)
- 2025年01月 (13件)
- 2024年12月 (22件)
- 2024年11月 (22件)
- 2024年10月 (20件)
- 2024年09月 (17件)
- 2024年08月 (24件)
- 2024年07月 (16件)
- 2024年06月 (13件)
- 2024年05月 (23件)
- 2024年04月 (17件)
- 2024年03月 (13件)
- 2024年02月 (19件)
- 2024年01月 (16件)
- 2023年12月 (27件)
- 2023年11月 (17件)
- 2023年10月 (14件)
- 2023年09月 (17件)
- 2023年08月 (17件)
- 2023年07月 (16件)
- 2023年06月 (18件)
- 2023年05月 (14件)
- 2023年04月 (16件)
- 2023年03月 (20件)
- 2023年02月 (14件)
- 2023年01月 (12件)
- 2022年12月 (21件)
- 2022年11月 (16件)
- 2022年10月 (17件)
- 2022年09月 (17件)
- 2022年08月 (16件)
- 2022年07月 (15件)
- 2022年06月 (20件)
- 2022年05月 (10件)
- 2022年04月 (14件)
- 2022年03月 (22件)
- 2022年02月 (15件)
- 2022年01月 (17件)
- 2021年12月 (18件)
- 2021年11月 (13件)
- 2021年10月 (24件)
- 2021年09月 (16件)
- 2021年08月 (17件)
- 2021年07月 (20件)
- 2021年06月 (14件)
- 2021年05月 (15件)
- 2021年04月 (20件)
- 2021年03月 (22件)
- 2021年02月 (10件)
- 2021年01月 (10件)
- 2020年12月 (15件)
- 2020年11月 (15件)
- 2020年10月 (16件)
- 2020年09月 (15件)
- 2020年08月 (19件)
- 2020年07月 (15件)
- 2020年06月 (14件)
- 2020年05月 (19件)
- 2020年04月 (12件)
- 2020年03月 (9件)
- 2020年02月 (18件)
- 2020年01月 (14件)
- 2019年12月 (23件)
- 2019年11月 (11件)
- 2019年10月 (15件)
- 2019年09月 (20件)
- 2019年08月 (12件)
- 2019年07月 (19件)
- 2019年06月 (19件)
- 2019年05月 (14件)
- 2019年04月 (11件)
- 2019年03月 (14件)
- 2019年02月 (10件)
- 2019年01月 (5件)
- 2018年12月 (16件)
- 2018年11月 (15件)
- 2018年10月 (15件)
- 2018年09月 (16件)
- 2018年08月 (6件)
- 2018年07月 (32件)
- 2018年06月 (17件)
- 2018年05月 (11件)
- 2018年04月 (24件)
- 2018年03月 (14件)
- 2018年02月 (8件)
- 2018年01月 (17件)
- 2017年12月 (15件)
- 2017年11月 (26件)
- 2017年10月 (22件)
- 2017年09月 (30件)
- 2017年08月 (24件)
- 2017年07月 (14件)
- 2017年06月 (27件)
- 2017年05月 (10件)
- 2017年04月 (23件)
- 2017年03月 (21件)
- 2017年02月 (14件)
- 2017年01月 (31件)
- 2016年12月 (25件)
- 2016年11月 (18件)
- 2016年10月 (17件)
- 2016年09月 (15件)
- 2016年08月 (9件)
- 2016年07月 (10件)
- 2016年06月 (19件)
- 2016年05月 (10件)
- 2016年04月 (13件)
- 2016年03月 (13件)
- 2016年02月 (14件)
- 2016年01月 (15件)
- 2015年12月 (26件)
- 2015年11月 (31件)
- 2015年10月 (31件)
- 2015年09月 (37件)
- 2015年08月 (40件)
- 2015年07月 (37件)
- 2015年06月 (40件)
- 2015年05月 (33件)
- 2015年04月 (33件)
- 2015年03月 (29件)
- 2015年02月 (32件)
- 2015年01月 (27件)
- 2014年12月 (29件)
- 2014年11月 (27件)
- 2014年10月 (31件)
- 2014年09月 (34件)
- 2014年08月 (34件)
- 2014年07月 (35件)
- 2014年06月 (48件)
- 2014年05月 (42件)
- 2014年04月 (38件)
- 2014年03月 (43件)
- 2014年02月 (38件)
- 2014年01月 (37件)
- 2013年12月 (43件)
- 2013年11月 (41件)
- 2013年10月 (44件)
- 2013年09月 (44件)
- 2013年08月 (41件)
- 2013年07月 (33件)
- 2013年06月 (39件)
- 2013年05月 (42件)
- 2013年04月 (28件)
- 2013年03月 (44件)
- 2013年02月 (41件)
- 2013年01月 (48件)
- 2012年12月 (48件)
- 2012年11月 (41件)
- 2012年10月 (42件)
- 2012年09月 (44件)
- 2012年08月 (40件)
- 2012年07月 (41件)
- 2012年06月 (44件)
- 2012年05月 (44件)
- 2012年04月 (41件)
- 2012年03月 (49件)
- 2012年02月 (41件)
- 2012年01月 (43件)
- 2011年12月 (45件)
- 2011年11月 (42件)
- 2011年10月 (49件)
- 2011年09月 (44件)
- 2011年08月 (41件)
- 2011年07月 (43件)
- 2011年06月 (49件)
- 2011年05月 (44件)
- 2011年04月 (41件)
- 2011年03月 (44件)
- 2011年02月 (42件)
- 2011年01月 (44件)
- 2010年12月 (46件)
- 2010年11月 (44件)
- 2010年10月 (48件)
- 2010年09月 (44件)
- 2010年08月 (45件)
- 2010年07月 (47件)
- 2010年06月 (44件)
- 2010年05月 (46件)
- 2010年04月 (43件)
- 2010年03月 (46件)
- 2010年02月 (42件)
- 2010年01月 (42件)
- 2009年12月 (42件)
- 2009年11月 (43件)
- 2009年10月 (41件)
- 2009年09月 (43件)
- 2009年08月 (41件)
- 2009年07月 (44件)
- 2009年06月 (35件)
- 2009年05月 (41件)
- 2009年04月 (46件)
- 2009年03月 (47件)
- 2009年02月 (41件)
- 2009年01月 (43件)
- 2008年12月 (45件)
- 2008年11月 (44件)
- 2008年10月 (43件)
- 2008年09月 (42件)
- 2008年08月 (38件)
- 2008年07月 (41件)
- 2008年06月 (38件)
- 2008年05月 (42件)
- 2008年04月 (41件)
- 2008年03月 (40件)
- 2008年02月 (37件)
- 2008年01月 (42件)
- 2007年12月 (47件)
- 2007年11月 (35件)
- 2007年10月 (40件)
- 2007年09月 (34件)
- 2007年08月 (36件)
- 2007年07月 (31件)
- 2007年06月 (36件)
- 2007年05月 (41件)
- 2007年04月 (22件)
- 2007年03月 (25件)
- 2007年02月 (23件)