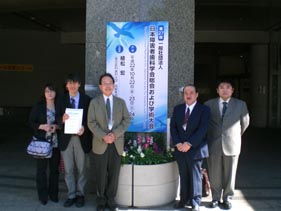乳幼児を持つ都内の保護者2000人を対象にした調査で、4分の3の乳幼児が、食べ物でないものを誤飲したか、しそうになったことがあることが、都生活安全課の調査で分かった。
大量誤飲で健康被害の恐れもある医薬品の誤飲が目立っており、都は水薬の容器に子供が開けにくい安全キャップを導入するなどの誤飲対策を検討する。
都は7月、0-6歳児を持つ保護者2000人を対象にインターネットを通じて「誤飲に関するヒヤリ・ハット調査」を実施、5801件の情報が寄せられた。
この結果、乳幼児が「誤飲したことがある」と回答したのは705人(35・3%)、「誤飲しそうになった経験がある」は807人(40・4%)で、両者を合わせると75・6%だった。
品目別で多かったのは、紙類(522件)やシール(502件)、医薬品(493件)。さらに誤飲で医療機関を受診した149件をみると、たばこ(46件)や医薬品(23件)、ビー玉(8件)が多かった。
27日に都庁で開催された「都商品等安全対策協議会」では、専門家から「薬局で処方される水薬(シロップの薬)の容器に安全キャップの導入を検討しては」などと意見が出された。海外では、安全キャップが義務化されている国もあるという。都は、今年度中に対象を医薬品に絞った誤飲調査を実施し、業界団体を協議会に招き、「安全キャップ」の導入が可能か検討する。