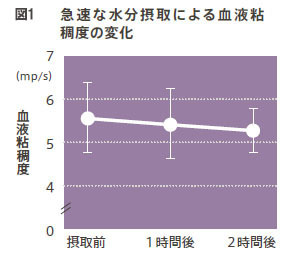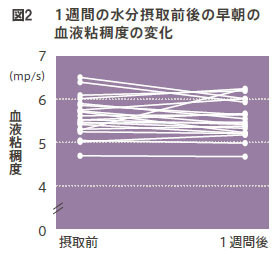全国17の私立歯科大や歯学部のうち、6割超が今年の入試で「定員割れ」になったことが4月27日、日本私立歯科大学協会のまとめで分かった。同協会では、私立歯科大や歯学部の志願者・入学者数の減少によって、次世代の歯科医の育成が困難になると危機感を強めている。
【関連記事】
医療機関の倒産、過去最悪の45件-昨年度
医師国試、合格率は89.2%
10年度診療報酬改定の内容などを説明―国公私立大学歯学部長・附属病院長会議
来年度の医学部入学定員は360人増―文科省
歯学教育の入学定員の「見直し」も
17の私立歯科大や歯学部のうち、入学者数が定員を下回ったのは11大学・学部(64.7%)で、入学者数と定員が同じなのが5大学・学部。入学者数が定員を上回ったのは昭和大歯学部のみだった。
定員割れの11大学・学部のうち、奥羽大歯学部では定員96人に対し、入学者数は3分の1の32人にとどまった。松本歯科大の入学者数も35人と、定員(80人)の半分を下回った。また、北海道医療大歯学部の入学者は、定員(96人)の半分の48人だった。全国17大学・学部の合計では、定員1891人に対し入学者は1489人。昨年と比べると定員は13人、入学者は213人減った。
歯科大・歯学部への入学者が減少している要因として同協会では、▽歯科医が過剰で、歯科医の多くがワーキング・プアだという根拠なき誤った情報が流布している▽国による国家試験合格率の調整で合格者が減少し、受験生らが卒業後の進路に不安を抱いている▽経済状況が悪化する中、高額な学費負担が志望をためらわせている-などを挙げている。
同協会では「このような状態が続けば、わが国の歯科医療制度の維持、増進に悪影響を及ぼす」などと指摘。国や大学、日本歯科医師会などの歯科界全体で早急に取り組むべき問題であるとの認識を示している。( 2010年04月27日 15:16 キャリアブレイン )