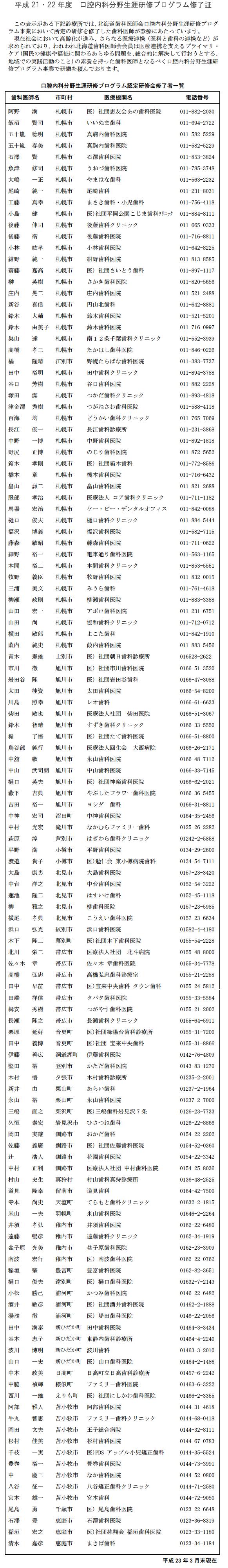ゴールデンウィークは、どのように過ごされましたか?
私は、テニス三昧でした。朝5時~8時まで行い、図書館や医院にて事務処理でした。これだけしか聞いているとなんて寂しい休日を思われるでしょうが、日頃たまった資料をこなしていくとストレス発散となります。でも、夜には元気がなくなり8時には、脳の活動が停止します。さようなら~ゴールデンウィーク!
記事一覧
5月4,5日休日の過ごし方
高齢者の摂食・嚥下機能障害を疑う問診のポイント
1)食事時間・食べ方の変化
2)食事内容、好みの変化
3)むせる
4)せきがでる
5)咽頭違和感、食物残留感
6)声の変化
7)痰の量の増加
8)食欲の低下
9)やせ、体重の変化
生涯医療費 歯できまる?
定期的に歯科医院を受診している人は、全ての病気にかかる年間の総医療費が低くなる傾向があることが、トヨタ関連部品健康保険組合(豊田市)と豊田加茂歯科医師会の共同調査で分かった。両団体は「歯をケアする人を増やし、医療費削減に役立ててほしい」と呼び掛けている。これまでの他県の健保組合の調査で高齢者層のデータはあったが、中年層は総医療費抑制につながるという明確なデータはなかったという。同組合の中村貞次理事は「歯をケアすると、高齢者以外でも総医療費を減らせることが分かった。歯周病にかかり始める35歳ぐらいから、しっかり歯を手入れすることが大切だ」と話している。
中日新聞 2011年3月28日
食事・発生 口の動き改善
食べ物をのみ込む時は、舌を上あごに押しつけて、喉に押し込む。その際は同時に、上あごの奥の軟らかい部分(軟口蓋)が上がって、口と鼻を結ぶ道路を塞いでいる。ところが、舌がんの手術後や、脳卒中の後遺症で舌や軟口蓋がまひすると、食べ物を押し込めなくなったり、誤って鼻の方に入ったりする。発声にも影響する。主に2種類の補助装置があり、ひとつは上あごの内側に装着する。舌が上あごに触れやすくなり、食べ物を喉に押し込みやすくなる。使い続けると、脳卒中のまひで不自由だった舌の動きが回復することもある。このタイプの補助装置は、口腔がんや脳卒中後の食事のリハビリを受けている患者に限り、保険がきく。もうひとつは、脳卒中によるまひなどで軟口蓋が上がらない場合、上あごに装着して軟口蓋を下から支えて持ち上げることで、食べ物が鼻に入らないようにする。使い続けると、軟口蓋の動きが回復し、不要になる場合もある。軟口蓋が上がらないと鼻に抜けたような感じの声になるため、発声障害の改善にも役立つ。上あごが生まれつき開いた口蓋裂の発音を直す装置として保険適用されている。
読売新聞 2011年3月24日
矯正治療は子どもだけのものだと思っていませんか?
矯正治療はあなたが望んだ時、いつもでもスタート出来ます。正しい咬み合わせは美しい笑顔と密接な関係があります。最近雑誌等でも多く取り上げられているので、大人になったから矯正治療を開始する方も増えています。でこぼこだと歯のお手入れが難しく、むし歯になりやすく、白いプラスティックを詰めたり、金属を被せたり、差し歯にしたり、抜いたりする治療が必要になります。また、歯周病で歯を支える骨が溶けぐらぐらしてきます。お手入れをしやすくすることによって、出来るだけ健康に、自分の歯を残す方法を、患者さんのライフスタイルに合わせて提案します。
北海道経済 5月号 №509
避難所の健康保持 口内ケアが大きな効果
東日本大震災の被災者が県内の避難所にも数多く身を寄せている。慣れない避難生活や被災のショックは免疫力を低下させ、健康疾患につながることが心配される。口の中を清潔にすることが、虫歯や歯周病だけでなく、細菌による誤嚥性肺炎やインフルエンザの発症を防ぎます。しかし、歯ブラシなどの用具や水がなく、歯磨きができる環境にない方もおられるかもしれません。歯ブラシの代わりに、スポンジ、ハンカチ、カーゼなどの布、綿、テイッシュ、綿棒を代用できます。何もなければ、自分の指や爪でもできます。奥歯から順番に前歯そして奥歯とこすっていきますが、裏側、表側、かむ面を1本ずつ丁寧にキュッ、キュッと音がするぐらいまでこすります。歯と歯の間は爪でこそげとり、もし、弁当のつまようじがあれば、けがをしないように先で汚れを落とします。つまようじにテイッシュを巻き、歯と歯の間の歯肉に入れ、歯間ブラシ代わりに使えます。血が出ても怖がらず奇麗にしてください。不潔、ビタミンC不足、過度のストレスなどが重なると歯肉は炎症を起こしやすくなりますから、まず清潔を心掛けてください。
新潟日報 2011年3月24日
免疫力をアップすると、どんないいことがあるの?
①花粉症の改善・予防ができる
免疫力は、体内に入ったアレルギー物質に体が反応するのを抑える力。スギ花粉が大量に飛ぶ春も、免疫力がしっかり働いていればマスクなしで過ごせます。
②がんになりにくい体になる
免疫力には、腫瘍の増殖を防ぐ働きがあります。たとえば、胃潰瘍やガンの発生を抑えたり小さくしたりするのも、免疫力の働きです。
③ウィルスに負けない体になる
免疫力は、体内に入った菌に抵抗する力。インフルエンザが流行る時期、体内に戦う力があれば元気に乗り切れます。
④歯周病の症状を緩和・予防ができる
細菌が侵入してきたときに、体内で応戦するのが免疫力。歯周病になったとき、外からのプラークコントロールに加え内側から抵抗する力があれば、症状を改善できます。
過去ログ
- 2025年12月 (15件)
- 2025年11月 (24件)
- 2025年10月 (26件)
- 2025年09月 (20件)
- 2025年08月 (22件)
- 2025年07月 (21件)
- 2025年06月 (12件)
- 2025年05月 (13件)
- 2025年04月 (5件)
- 2025年03月 (11件)
- 2025年02月 (11件)
- 2025年01月 (13件)
- 2024年12月 (22件)
- 2024年11月 (22件)
- 2024年10月 (20件)
- 2024年09月 (17件)
- 2024年08月 (24件)
- 2024年07月 (16件)
- 2024年06月 (13件)
- 2024年05月 (23件)
- 2024年04月 (17件)
- 2024年03月 (13件)
- 2024年02月 (19件)
- 2024年01月 (16件)
- 2023年12月 (27件)
- 2023年11月 (17件)
- 2023年10月 (14件)
- 2023年09月 (17件)
- 2023年08月 (17件)
- 2023年07月 (16件)
- 2023年06月 (18件)
- 2023年05月 (14件)
- 2023年04月 (16件)
- 2023年03月 (20件)
- 2023年02月 (14件)
- 2023年01月 (12件)
- 2022年12月 (21件)
- 2022年11月 (16件)
- 2022年10月 (17件)
- 2022年09月 (17件)
- 2022年08月 (16件)
- 2022年07月 (15件)
- 2022年06月 (20件)
- 2022年05月 (10件)
- 2022年04月 (14件)
- 2022年03月 (22件)
- 2022年02月 (15件)
- 2022年01月 (17件)
- 2021年12月 (18件)
- 2021年11月 (13件)
- 2021年10月 (24件)
- 2021年09月 (16件)
- 2021年08月 (17件)
- 2021年07月 (20件)
- 2021年06月 (14件)
- 2021年05月 (15件)
- 2021年04月 (20件)
- 2021年03月 (22件)
- 2021年02月 (10件)
- 2021年01月 (10件)
- 2020年12月 (15件)
- 2020年11月 (15件)
- 2020年10月 (16件)
- 2020年09月 (15件)
- 2020年08月 (19件)
- 2020年07月 (15件)
- 2020年06月 (14件)
- 2020年05月 (19件)
- 2020年04月 (12件)
- 2020年03月 (9件)
- 2020年02月 (18件)
- 2020年01月 (14件)
- 2019年12月 (23件)
- 2019年11月 (11件)
- 2019年10月 (15件)
- 2019年09月 (20件)
- 2019年08月 (12件)
- 2019年07月 (19件)
- 2019年06月 (19件)
- 2019年05月 (14件)
- 2019年04月 (11件)
- 2019年03月 (14件)
- 2019年02月 (10件)
- 2019年01月 (5件)
- 2018年12月 (16件)
- 2018年11月 (15件)
- 2018年10月 (15件)
- 2018年09月 (16件)
- 2018年08月 (6件)
- 2018年07月 (32件)
- 2018年06月 (17件)
- 2018年05月 (11件)
- 2018年04月 (24件)
- 2018年03月 (14件)
- 2018年02月 (8件)
- 2018年01月 (17件)
- 2017年12月 (15件)
- 2017年11月 (26件)
- 2017年10月 (22件)
- 2017年09月 (30件)
- 2017年08月 (24件)
- 2017年07月 (14件)
- 2017年06月 (27件)
- 2017年05月 (10件)
- 2017年04月 (23件)
- 2017年03月 (21件)
- 2017年02月 (14件)
- 2017年01月 (31件)
- 2016年12月 (25件)
- 2016年11月 (18件)
- 2016年10月 (17件)
- 2016年09月 (15件)
- 2016年08月 (9件)
- 2016年07月 (10件)
- 2016年06月 (19件)
- 2016年05月 (10件)
- 2016年04月 (13件)
- 2016年03月 (13件)
- 2016年02月 (14件)
- 2016年01月 (15件)
- 2015年12月 (26件)
- 2015年11月 (31件)
- 2015年10月 (31件)
- 2015年09月 (37件)
- 2015年08月 (40件)
- 2015年07月 (37件)
- 2015年06月 (40件)
- 2015年05月 (33件)
- 2015年04月 (33件)
- 2015年03月 (29件)
- 2015年02月 (32件)
- 2015年01月 (27件)
- 2014年12月 (29件)
- 2014年11月 (27件)
- 2014年10月 (31件)
- 2014年09月 (34件)
- 2014年08月 (34件)
- 2014年07月 (35件)
- 2014年06月 (48件)
- 2014年05月 (42件)
- 2014年04月 (38件)
- 2014年03月 (43件)
- 2014年02月 (38件)
- 2014年01月 (37件)
- 2013年12月 (43件)
- 2013年11月 (41件)
- 2013年10月 (44件)
- 2013年09月 (44件)
- 2013年08月 (41件)
- 2013年07月 (33件)
- 2013年06月 (39件)
- 2013年05月 (42件)
- 2013年04月 (28件)
- 2013年03月 (44件)
- 2013年02月 (41件)
- 2013年01月 (48件)
- 2012年12月 (48件)
- 2012年11月 (41件)
- 2012年10月 (42件)
- 2012年09月 (44件)
- 2012年08月 (40件)
- 2012年07月 (41件)
- 2012年06月 (44件)
- 2012年05月 (44件)
- 2012年04月 (41件)
- 2012年03月 (49件)
- 2012年02月 (41件)
- 2012年01月 (43件)
- 2011年12月 (45件)
- 2011年11月 (42件)
- 2011年10月 (49件)
- 2011年09月 (44件)
- 2011年08月 (41件)
- 2011年07月 (43件)
- 2011年06月 (49件)
- 2011年05月 (44件)
- 2011年04月 (41件)
- 2011年03月 (44件)
- 2011年02月 (42件)
- 2011年01月 (44件)
- 2010年12月 (46件)
- 2010年11月 (44件)
- 2010年10月 (48件)
- 2010年09月 (44件)
- 2010年08月 (45件)
- 2010年07月 (47件)
- 2010年06月 (44件)
- 2010年05月 (46件)
- 2010年04月 (43件)
- 2010年03月 (46件)
- 2010年02月 (42件)
- 2010年01月 (42件)
- 2009年12月 (42件)
- 2009年11月 (43件)
- 2009年10月 (41件)
- 2009年09月 (43件)
- 2009年08月 (41件)
- 2009年07月 (44件)
- 2009年06月 (35件)
- 2009年05月 (41件)
- 2009年04月 (46件)
- 2009年03月 (47件)
- 2009年02月 (41件)
- 2009年01月 (43件)
- 2008年12月 (45件)
- 2008年11月 (44件)
- 2008年10月 (43件)
- 2008年09月 (42件)
- 2008年08月 (38件)
- 2008年07月 (41件)
- 2008年06月 (38件)
- 2008年05月 (42件)
- 2008年04月 (41件)
- 2008年03月 (40件)
- 2008年02月 (37件)
- 2008年01月 (42件)
- 2007年12月 (47件)
- 2007年11月 (35件)
- 2007年10月 (40件)
- 2007年09月 (34件)
- 2007年08月 (36件)
- 2007年07月 (31件)
- 2007年06月 (36件)
- 2007年05月 (41件)
- 2007年04月 (22件)
- 2007年03月 (25件)
- 2007年02月 (23件)