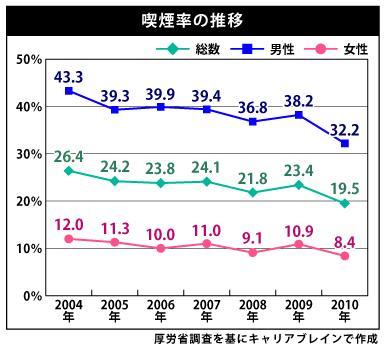北海道感染症情報センターは10日、全道のインフルエンザ患者報告数が警報レベル(定点医療機関当たり30人)に達したと発表した。全道での警報は新型インフルエンザが流行した09年10月以来、2シーズンぶり。
同センターによると、1月30日~2月5日に道内の定点医療機関から報告された患者数は定点当たり平均42・15人で、前週(20・94人)の2倍超と大幅に増加。全国(42・62人)とほぼ同じ規模の深刻な流行となっている。
地域別では、30保健所管内中18管内で警報レベル、9管内で注意報レベル(定点当たり10人)を超えた。また、29管内で報告数が前週より増加した。
定点あたりの患者数が最も多いのは岩見沢の100・25人で前週の約3倍。50人に達した地域は、57・96人に達した札幌市など計8保健所に上った。
また厚生労働省によると、同じ1月30日~2月5日の間に道内の小中高校、保育所、幼稚園でインフルエンザとみられる症状を訴えた園児、児童、生徒は6526人で、前週の約2・7倍に上った。6日以降も流行は拡大し続けており、道はマスク着用などの感染予防を呼びかけている。