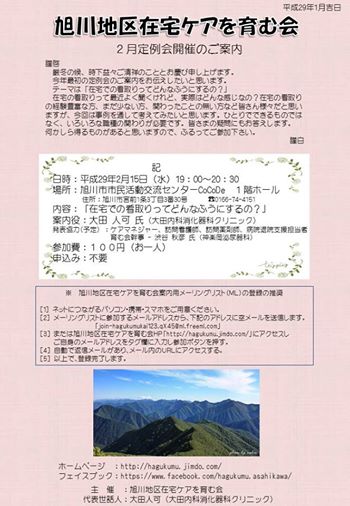兵庫県健康福祉部健康局薬務課が県内の薬局薬剤師を対象に実施した「薬剤師がお薦めするジェネリック医薬品(GE薬)」の調査結果がこのほどまとまった。飲みやすさや味などを評価する声が多く、3軒以上の薬局から評価された「お薦めGE薬」は合計で178品目に達した。同県薬務課はこの調査結果を、患者に応じた適切なGE薬を薬局などで選択する際の参考資料として役立ててもらい、GE薬の使用促進につなげたい考えだ。
調査は昨年10、11月に実施。県内の2582薬局を対象に郵送で調査票を配布し、患者に人気があるGE薬、調剤しやすいGE薬など、薬剤師自身が薦めるGE薬を各薬局から最大10品目提示してもらった。小児用剤、OD錠、錠剤・カプセル剤、散剤・顆粒剤、液剤、貼付剤、軟膏剤・クリーム剤・ローション外用液剤、点眼剤・点鼻剤、坐剤、吸入剤など領域ごとに具体的な品目名を記入してもらい、その推奨理由も聞いた。821薬局から回答があった(回収率31.8%)
調査の結果、合計1074品目の「お薦めGE薬」がリストアップされた。このうち3軒以上の薬局から評価を得たのは178品目。その内訳は、小児用剤18品目、錠剤、カプセル剤、散剤、液剤などの内服薬116品目、外用薬44品目となっていた。
最も多くの支持を集めたのは帝國製薬の「ビーソフテンローション0.3%」(先発品:ヒルドイドローション0.3%)。「使用感がさらっとして使いやすい」「化粧水のようなタイプで夏場には最適」「スプレータイプなので広範囲に塗りやすい」など、塗り心地の良さを136薬局が評価した。
同じ先発品については日医工の「ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%『日医工』」も「逆さまにして背中等にも噴霧可能」など、容器の工夫が25薬局から支持された。
先発品にはない剤形や大きさが38薬局から評価されたのは、持田製薬の「バラシクロビル粒状錠500mg『モチダ』」(先発品:バルトレックス錠500)。「粒が小さく高齢者が服用しやすい」「粒が小さくゲル化するので飲み込みやすい」などの声が上がった。
点眼剤では千寿製薬の「ティアバランス点眼液0.1%」(先発品:ヒアレイン点眼液0.1%)が、「容器が柔らかくさしやすい」などと容器の工夫が10薬局から評価された。同じ先発品については、日本点眼薬研究所の「ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%『日点』」も防腐剤を含まないことが18薬局から支持を集めた。
小児用剤では、高田製薬の「クラリスロマイシンDS小児用10%『タカタ』」(先発品:クラリスドライシロップ10%小児用)が好評で、「苦みが少ない」「バナナ味」など味の良さが94薬局から高い評価を受けた。同社の他の複数の小児用剤も同様の理由で評価を獲得している。
貼付剤では、大石膏盛堂の「パテルテープ20」(先発品:モーラステープ20mg)の使用感の良さが、「先発品と変わらない貼り心地」など14薬局から評価を受けた。
日医工の「バルプロ酸ナトリウムシロップ5%『日医工』」(先発品:デパケンシロップ5%)は「量り間違いによる飲み間違いが減少する」「1回分使い切り個包装」など、包装の工夫が17薬局から評価された。キョーリンリメディオの「モンテルカスト錠10mg『KM』」(先発品:キプレス錠10mg)など、オーソライズドジェネリックであり先発品との価格差が大きい品目も、薬剤師から支持を集めた。
このほか全体的に、錠剤表面の印字や割線、OD錠の欠けにくさ、独自の剤形、嚥下困難患者の服用のしやすさなどを評価する声が上がった。
これらの調査結果について同県薬務課長の四方浩人氏は「全体を通じて、飲みやすさや味の良さを評価する声が多かった」と話す。結果は既に県内の薬局などにフィードバックした。最適なGE薬を選択する際の参考資料として役立ててもらい、使用促進を図りたいとしている。