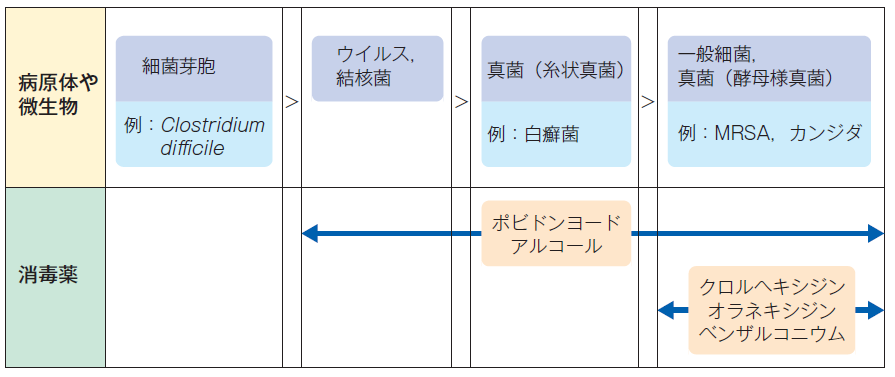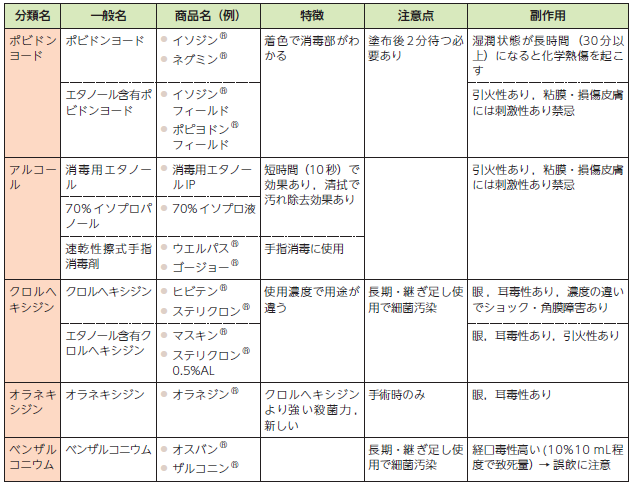全国保険医団体連合会は6月21日、記者会見を開き、約1万施設への調査で、マイナ保険証トラブルを経験したのは65.1%に上るという最終結果を公表した。トラブルの内容は、マイナ保険証で「無効・該当資格なし」との内容が最多で65.1%、その対応法として「健康保険証で資格確認した」が74.9%で最も多かった。
資格確認できず、医療機関の窓口でいったん10割を請求したのは、38都道府県1291件、「他人の情報がひも付けされていた」が31都道府県114件と、トラブルは各地域で発生している。その他、他人の顔でもマイナ保険証が認証された事例が把握できただけでも3件、障害者手帳のひも付けミスなども発覚している。
衆参両院の国会議員に対して緊急アンケートを実施したところ、回答があったのは62人で回答率は10%に満たず、自民、公明両党の議員からは回答がなかった(6月14日~20日に実施)。62人の回答は、保険証について「廃止に反対」が55人(88.7%)、マイナ保険証を起点とするオンライン資格確認システムの運用について「いったん停止して総点検すべき」が57人だった(91.9%)。
保団連会長の住江憲勇氏は、▽さまざまなトラブルが噴出する中で、個人にとっての機微情報に富む医療情報をマイナンバーカードにひも付けることの危険性、▽申請主義の資格確認書により無保険者を作り出す懸念、▽ヒューマンエラーを起こさない制度設計を政府は怠りながら、さまざまなトラブルをヒューマンエラーに矮小化し、現場に責任を押し付ける政府の危機管理意識の欠如、▽結果として国民にとっても、医療現場にとってもマイナ保険証の利用は危険であり、利用に堪えない状況になっている――という4点を指摘。
住江会長は、「直ちに運用停止、全件チェック、全容解明し、解決策および再発防止に取り組み、それを国民に明らかにすることこそが、政府が取るべき喫緊の課題だ」と訴えた。
保団連では、今秋にも衆議院の解散を想定し、「待合室から健康保険証を存続させるキャンペーン」を実施する。具体的には、▽保険証廃止法案に対する各党採決結果を記した待合室掲示用ポスター、▽保険証廃止知っとくパンフレット(マイナ保険証トラブル回避法、資格確認書などを現時点の到達に基づき患者に分かりやすく解説したパンフレット)、▽ショート動画(記者会見参加医師、歯科医師の発言を素材としたショート動画)、▽国会質疑での各党の姿勢、個別議員アンケート――などを作成、展開する。