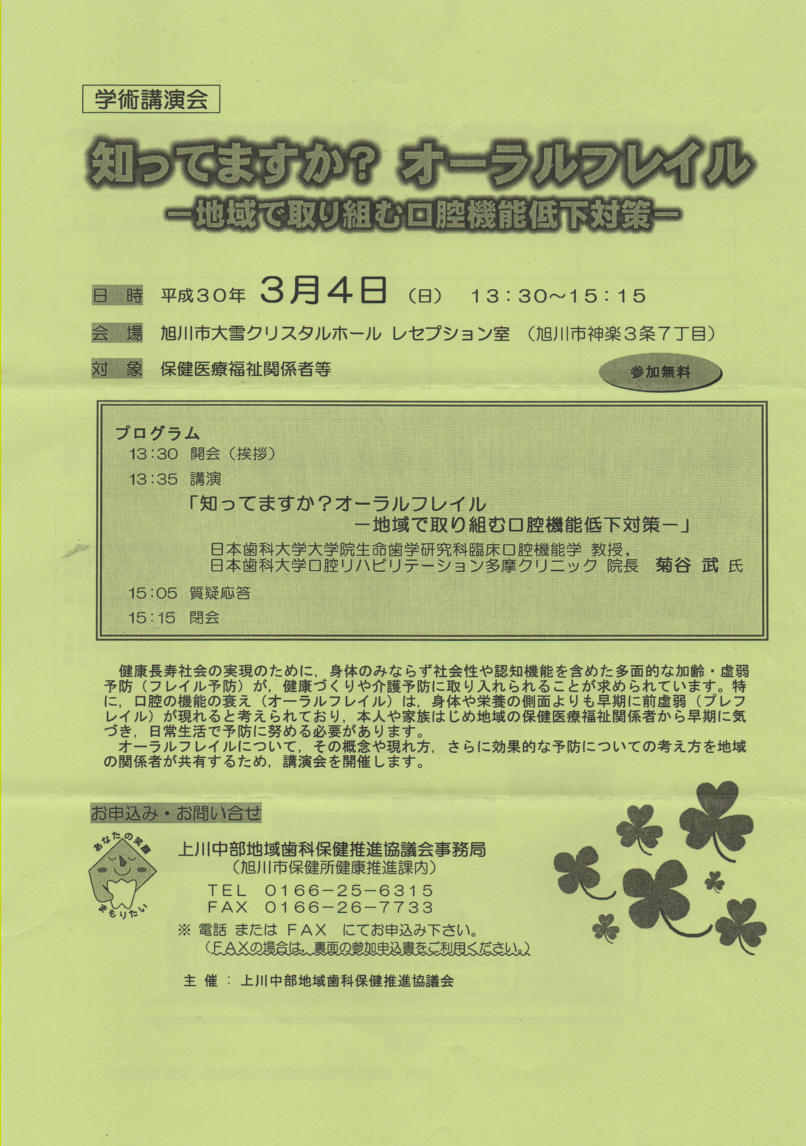関西を中心とした有志の歯科医師らがモンゴルの遊牧民らに虫歯予防の指導を続けている。約27年にわたる草の根活動。年に2回の訪問で現地診療を行い、設立に協力した首都ウランバートルの医療施設も完成した。かつて日本でも見られた食生活の近代化に伴う虫歯の増加を防ぐため、息長く取り組んでいる。
昨年秋、ウランバートルから車で10時間ほどの小さな村。活動を中心となって進める兵庫県明石市の歯科医黒田耕平(くろだ・こうへい)さん(66)が診療指導で目にした2歳の男児は20本の乳歯全てが虫歯だった。
歯茎は歯ブラシが触れただけで出血し、口内はすぐ真っ赤に。こうした光景は「決して珍しくない」という。暴れる子の口を開けるのは難しいが、口元に添える左手の指の置き方などに気を使い、手際よく診察。黒田さんの手元を現地の歯科医らが脇で食い入るように見つめていた。
1991年、初めてのモンゴルで受けた衝撃が黒田さんには今も記憶に残る。肉と乳製品中心の食生活を送る遊牧民にはないと思っていた虫歯が若者を中心に広がっていたからだ。
民主化に伴う輸入菓子の増加、遊牧生活から都市定住へのライフスタイル転換に伴う食生活の急変...。重なって見えたのは、高度経済成長期の日本だ。「日本では虫歯が減るまで約40年かかったが、人口が少ないモンゴルなら、20年でできないか」
大阪府交野市から救急車を譲り受け、遊牧民が住むテント式住居「ゲル」への訪問診療を開始。使われなくなった歯ブラシの植毛機を日本から送り、現地生産も。94年には幼稚園の一室に歯科診療所を開設した。
それから約23年。昨年9月、診療所の収益や寄付を基にウランバートルで完成したのが「エネレル健康センター」。エネレルはモンゴル語で慈愛を意味し、歯科だけでなく、内科も入る。所長には岡山大歯学部で研修を受けた歯科医のイチンホルローさんが就いた。
黒田さんは「活動に参加してくれた延べ400人以上の日本人ボランティアや、現地医師の協力のおかげ」と振り返る。
今後は専門の小児障害者歯科の普及にも力を入れるつもりだ。「現地では歯科医らがどう対応していいか分からず、障害のある患者を帰宅させる現状もある。障害者を診られる歯科医を増やしたい」と意気込む。